皆さん、日々の業務の中で下請け企業とのやり取りに戸惑ったことはありませんか?
特に、マネジメントに携わる立場としては、「これって法律的に大丈夫かな?」「取引先に不利益を与えていないだろうか?」と不安になる場面もあるはずです。
そんな時に必ず押さえておきたいのが、「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」です。
これは、親事業者が下請け事業者に対して適正な取引を行うために設けられた大切な法律です。
もしも、このルールを知らずに取引を進めてしまえば、思わぬトラブルを引き起こしたり、最悪の場合、信頼を失うことにもなりかねません。
逆に言えば、この法律をしっかり理解しておくことで、下請け企業との信頼関係を強化でき、あなた自身のマネジメント力や評価も大きく高まるはずです!
この記事では、管理職を目指すあなたが知っておくべき 「下請法の4つの重要ポイント」 を、分かりやすく一つずつ整理しました。
下請け事業者との関係性を円滑に保つためにも、知らずに違反しないように、正確な知識を身につけておきましょう。
現場で「知っていて良かった!」と思えるように、ぜひ最後まで目を通してください!
多彩な資格がスマートフォンで手軽に本格的な学習ができるオンライン試験対策講座
【設問①】支払い期日は「できる限り短い期間内」であれば自由に定めて良い?
設問①
下請け代金の支払い期日は、親事業者が下請け事業者の給付を受領した日から、出来る限り短い期間内において定めなければならないが、具体的な日数の制限までは定められていない。
回答:誤り
▼ 解説
下請法では、下請け代金の支払い期日について、単に「できる限り短い期間」としているわけではありません。
実は、親事業者は給付を受領した日から原則として60日以内に下請け代金を支払わなければならないと、具体的な日数制限が設けられています。
この点を誤解して、「とりあえず早めに払えばいい」と思い込むと、下請法違反になる可能性があります。
支払いの遅延は、下請け事業者にとっては資金繰りを直撃します。
特に、部門長や管理職を目指す方は、この60日ルールを守る体制を社内で徹底する必要があります。
▼ 要約
 下請法では支払い期日を「できる限り短く」するだけではなく、原則60日以内の具体的な期限が決められています。
下請法では支払い期日を「できる限り短く」するだけではなく、原則60日以内の具体的な期限が決められています。
▼ さらにわかりやすい要約
 支払い期日は「原則60日以内」。
支払い期日は「原則60日以内」。
 「早めに払えばOK」という認識では不十分!
「早めに払えばOK」という認識では不十分!
【設問②】下請け事業者に書面を交付する義務があるか?
設問②
下請け事業者に対して、物品の製造委託をした親事業者は、原則として、直ちに、下請け事業者の給付等の内容、下請け代金の額、支払い期日及び支払い方法等の所定の事項を記載した書面を下請け事業者に交付しなければならない。
回答:正しい
▼ 解説
下請法では、親事業者が下請け事業者に業務を委託した場合には、
「給付内容・代金の額・支払い期日・支払い方法」などの重要事項を明記した書面を交付することが義務付けられています。
この書面は、発注内容を明確化し、後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。
なお、近年では電子データ(PDFなど)で交付することも認められていますが、相手方の同意が必要です。
責任ある管理職を目指す立場としては、発注内容を曖昧にせず、確実に書面化することを徹底しましょう。
▼ 要約
 下請法では、発注内容の書面交付が義務です。
下請法では、発注内容の書面交付が義務です。
 書面に必要事項を明記して、トラブル防止!
書面に必要事項を明記して、トラブル防止!
▼ さらにわかりやすい要約
 必ず「書面」で伝える!
必ず「書面」で伝える!
 電子でもOKだが、同意が必須!
電子でもOKだが、同意が必須!
【設問③】欠陥があった給付物を下請け業者に引き取らせるのは違反?
設問③
下請け事業者に対して、物品の製造委託をした親事業者は、下請け事業者の責めにすべき理由に基づく欠陥があった時は、下請け事業者の給付を受領した後に、下請け事業者に当該給付にかかるものを、引き取らせても下請法には違反しない。
回答:正しい
▼ 解説
下請法では、下請け事業者に責任のある欠陥があった場合には、親事業者は給付物を引き取らせることが認められています。
これは当然のことであり、欠陥品をそのまま引き取らないと、親事業者側の損失が大きくなるためです。
ただし、下請け側に責任がない場合に一方的に返品を押し付けることは、下請法違反となるので注意しましょう。
返品が適正かどうかの判断には、記録を残すことが重要です。
▼ 要約
 下請け側に責任がある欠陥なら、返品OK!
下請け側に責任がある欠陥なら、返品OK!
 責任がないのに返品するのはNG!
責任がないのに返品するのはNG!
▼ さらにわかりやすい要約
 欠陥が「下請け責任」なら引き取らせるのは合法!
欠陥が「下請け責任」なら引き取らせるのは合法!
 記録を残して証拠を明確に!
記録を残して証拠を明確に!
【設問④】親事業者が指定したものを強制的に購入させることはできる?
設問④
下請け事業者に対して、物品の製造を委託した親事業者は、下請け事業者の給付の内容を均質にし、または、その改善を図るため必要がある場合であっても、下請け事業者に自己の指定するものを強制して購入させることができない。
回答:誤り
▼ 解説
下請法では、「購入・利用強制」は原則として禁止されています。
しかし、給付内容の均質化や改善のためにどうしても必要な場合は、例外として指定購入を求めることができます。
ただし、この場合でも必要性が正当でなければなりませんし、不当に高額なものを買わせるなどは当然NGです。
無理な買い取りの強制は、「優越的地位の濫用」として違法となる可能性が高いため、判断は慎重に行いましょう。
▼ 要約
 給付の均質化など正当な理由があれば、指定購入は可能!
給付の均質化など正当な理由があれば、指定購入は可能!
 不当な強制はNG!
不当な強制はNG!
▼ さらにわかりやすい要約
 必要性があるならOK!
必要性があるならOK!
 優越的地位の濫用に注意!
優越的地位の濫用に注意!
【まとめ】下請法の基本を守って信頼関係を築こう!
管理職を目指す皆さんにとって、下請け事業者との取引は信頼関係の構築が何より大切です!
下請法のポイントを抑え、法律違反を未然に防ぐ体制を整えましょう。
 支払い期日は原則60日以内!
支払い期日は原則60日以内!
 必ず書面で発注内容を交付する!
必ず書面で発注内容を交付する!
 責任がある欠陥なら返品OK!
責任がある欠陥なら返品OK!
 必要なら指定購入も可能だが、強制しすぎはNG!
必要なら指定購入も可能だが、強制しすぎはNG!
このように、正しい知識を持つことで、下請け業者との取引を公正かつスムーズに進めることができます。
日頃から社内教育や取引先とのコミュニケーションを大切にし、信頼される管理職を目指しましょう!
【さらに分かりやすい要約】
 支払い・書面交付・返品・購入強制の4つを覚えておけば、下請法の基本は完璧!
支払い・書面交付・返品・購入強制の4つを覚えておけば、下請法の基本は完璧!
 法律を守ることは、会社の信用を守ることにつながります!
法律を守ることは、会社の信用を守ることにつながります!
 「下請法を守る=取引先に選ばれ続ける秘訣」です!
「下請法を守る=取引先に選ばれ続ける秘訣」です!
▼おすすめ関連記事もチェック!
 企業活動に関する法規則とは?~管理職なら知っておくべき13のポイント!~
企業活動に関する法規則とは?~管理職なら知っておくべき13のポイント!~
 個人情報保護法の重要ポイント5選|意外と勘違いしやすい知っておきたい実務知識!
個人情報保護法の重要ポイント5選|意外と勘違いしやすい知っておきたい実務知識!
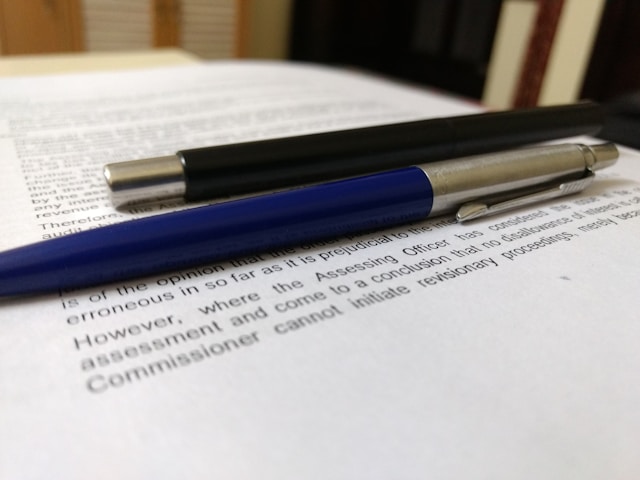


コメント