はじめに|「安全への配慮」が問われる時代に
「納品した製品が事故を起こし、顧客がケガをした」
「どこが悪かったのか調査が始まり、社内は混乱している」
「仕入れ先の製品なのに、なぜか自社が責任を問われている・・・」
管理職を目指すあなたにとって、このような場合、どう対応しますか?トラブルは突然起こり、そのとき真っ先に対応を求められるのは、” 現場の責任者 ”です。
日々のビジネスの現場において、製品の安全性が企業の信頼を左右する時代になっています。特に、製造・販売・輸入に関わる業務においては、「製造物責任法(PL法)」の理解は不可欠です。
管理職を目指すあなたにとって、「責任の所在を正確に把握しておく」ことは、リスクマネジメント上、極めて重要なスキルと言えるでしょう。
だからこそ、法律の基本的な知識を身につけておくことは重要であり、本記事では、ビジネス実務法務検定試験2級で出題される「製造物責任法」の5つの重要ポイントを、具体的な設問形式で分かりやすく解説していきます。さらに、試験対策として、関連書籍や通信講座も紹介します。
問題①|加工された農林水産物は「製造物」に含まれるのか?
設問:
製造物責任法上の「製造物」とは、製造または加工された動産を指すが、農林水産物はたとえ加工されていても、製造物には該当しない。
回答: 誤り
解説:
製造物責任法において、「製造物」とは基本的に「動産」を指します。ここでの「動産」とは、簡単に言えば、机や家電、食品などの動かせる物全般です。
ただし、例外として「農林水産物」は、たとえそれが加工されたものであっても、製造物には該当しないと定義されています。したがって、「加工されていれば製造物」という単純な考え方は誤りです。
実務では、「冷凍の魚」や「カットされた野菜」などが加工されていても、法律上は「製造物」とはみなされないことに注意しましょう。
要約:
農林水産物は、加工されていても「製造物責任法」の対象外です。
加工した魚や野菜でも、PL法では「製造物」とは認められません!
問題②|海外から輸入しただけの企業に責任はある?
設問:
製造物を現実に製造せず、業として海外から輸入した者は、製造物責任法上の製造業者等に該当することはない。
回答: 誤り
解説:
製造物責任法では、「製造業者等」という定義に、「製造した者」だけでなく、「業として輸入した者」も含まれます。つまり、たとえ日本国内で製造していなくても、海外から業として輸入した場合には、その輸入業者にも製造業者としての責任が課されるのです。
この点は、グローバル調達が進む現代において極めて重要です。輸入部門や商社などでは、この責任の所在をきちんと認識しておかなければ、思わぬ法的トラブルに発展する恐れがあります。
要約:
輸入業者も「製造業者」として責任を問われることがあります。
作ってなくても、輸入して売ればPL法の責任がある!
問題③|販売だけの小売業者は責任を問われない?
設問:
製造物を現実に製造せず、メーカーから製造物を仕入れ、これを消費者に販売する小売業者は、原則として、製造物責任法上の製造業者等に該当しない。
回答: 正しい
解説:
製造物責任法では、製造や輸入に関与していない「通常の小売業者」は、原則としてPL法の「製造業者等」には該当しません。つまり、製造元や輸入元が明らかである限り、小売業者が直接責任を負うことはないのです。
ただし、例外があります。たとえば、製造業者や輸入業者が誰なのかを明らかにできない場合などには、小売業者が製造業者等とみなされることもあるため、慎重な対応が求められます。
要約:
小売業者は、通常はPL法の責任対象ではありません。
ふつうに売るだけの店は、PL法の責任を負いません!
問題④|被害が人に及ばないと、PL法は使えない?
設問:
製造物責任法に基づく損害賠償責任が成立するためには、製造物の欠陥によって人の生命または身体に被害が生じる必要があり、単に製造物自体が破損した場合や、製造物以外のものに損害が拡大した場合は、製造物責任法が適用されない。
回答: 誤り
解説:
製造物責任法は、「生命・身体への被害」だけでなく、「他の財物への損害」にも適用されるとされています。つまり、欠陥製品によって周囲の家具が壊れた、というようなケースでも、PL法の対象になります。
ただし、製品それ自体の損傷のみ(=自爆的な壊れ方)は、PL法の適用外です。これは非常に混同されやすいので、試験でも狙われやすいポイントです。
要約:
PL法は、人への被害だけでなく、他のモノへの被害にも適用されます。
モノが壊れても、人以外に被害があればPL法が使えます!
問題⑤|「警告不足」だけでは欠陥とは言えない?
設問:
製造物責任法に基づく損害賠償責任が成立するためには、製造物に物理的な欠陥があるということが必要であり、製造物の安全性に関する指示や警告に欠陥があったというだけでは、製造物責任法上の欠陥とは認められない。
回答: 誤り
解説:
製造物責任法における「欠陥」とは、製品の設計上の欠陥、製造過程での欠陥、さらに「警告・表示上の欠陥」までを含みます。したがって、適切な使用方法や危険性を説明しなかったこと自体も「欠陥」と認められるのです。
例えば、「高温になる電気ポットに注意書きがなかった」というだけでも、PL法上の責任が問われる可能性があります。これは、製造物の物理的な問題だけでなく、「情報提供の不備」も対象になるということを意味しています。
要約:
「警告の欠如」も、PL法上の欠陥にあたります。
説明不足も、欠陥になるんです!
【解説】製造物責任法(PL法)とは?
1. 製造物責任法って何?
製造物責任法(英語では Product Liability Law)は、1995年に施行された法律で、「欠陥のある製品によって消費者がケガや損害を受けた場合、製造者が損害賠償責任を負う」ことを定めたものです。
つまり、製品を作った会社や輸入した会社は、
「ちゃんと作ったつもり」でも、
「もし欠陥があって事故が起きたら責任を取ってくださいね」
というルールです。
→このような法律の基礎を体系的に学ぶのに、ビジネス実務法務検定試験の学習が効果的です。
2. なぜこの法律が必要だったのか?
以前は、「製造者に過失があったと証明できなければ、損害賠償は難しい」とされていました。
しかし現代では、製品は複雑化・多様化し、消費者が原因を特定するのは困難です。
そこでこの法律では、「過失の有無」ではなく「欠陥の有無」で責任を判断する」という仕組みにしました。
これを「無過失責任」と言います。
3. PL法で対象になる“欠陥”とは?
製造物責任法で問題になる「欠陥」には、以下の3つがあります:
① 設計上の欠陥
…そもそもの設計ミス。使い方を守っていても危険な場合。
② 製造上の欠陥
…製品の一部に製造ミスや不具合がある場合。
③ 表示上の欠陥(警告の不備)
…危険な使い方をしないように、適切な説明や注意書きがない場合。
4. PL法の対象となるもの
● 対象になるのは?
→ 製造・加工された動産(=モノ)です。
家電、車、食品、家具など、基本的に「動かせる製品」が対象です。
● 対象にならないものは?
→ 建物や土地は対象外。また、農林水産物(野菜や魚など)も、たとえ加工されていても対象外です。
5. 責任を問われるのは誰?
- 製造した会社(メーカー)
- ブランドだけをつけている会社(名義貸し)
- 海外から輸入した会社(輸入業者)
これらは全て、「製造業者等」として責任を問われます。
※小売店など、単に販売しているだけの業者は基本的に対象外ですが、製造者が不明な場合には責任を負うことがあります。
6. PL法でカバーされる損害とは?
以下のような損害が対象です:
- 人の生命や身体への被害(例:やけど、骨折など)
- 他の財産への被害(例:火災による家具の損害)
※ただし、製品自体だけが壊れた場合はPL法の対象外となり、契約上の責任で対応します。
7. 管理職が気をつけるべきポイント
- 製品マニュアルや注意表示に警告の不備がないかをチェック!
- 仕入れ先や製造元の明確化が重要!(責任の所在を明確に)
- 事故発生時には、初動対応と事実関係の整理を迅速に!
まとめ:製造物責任法とは?
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 法律の目的 | 欠陥製品による事故から消費者を守る |
| 対象 | 製造・加工された「動産」 |
| 欠陥の種類 | 設計・製造・表示の欠陥 |
| 責任を負う者 | 製造者、輸入業者、名義貸し業者 |
| 管理職の備え | 表示の確認・責任の明確化・初動対応の準備 |
超簡単に一言で言うと?
「欠陥ある製品で人やモノに被害が出たら、作った人(会社)が責任を取る法律」
あなたの学びをさらに深める!おすすめ教材リンク
- 【公式テキストで学ぶ】→ [ビジネス実務法務検定試験(R)2級公式テキスト〈2025年度版〉 [ 東京商工会議所 ]]
- 【短期間で合格を狙うなら!】→ [多彩な資格がスマートフォンで手軽に本格的な学習ができるオンライン試験対策講座]
- 【初学者向け・動画で学べる】→ [様々な資格学習が1078円でウケホーダイ!【オンスク.JP】]
まとめ|管理職に求められるのは「知識」と「リスク感度」
製造物責任法は、製造に直接関わっていなくても、あなたのビジネスに関係してくる可能性があります。とくに、リーダーや管理職を目指す方にとっては、製品安全に対する責任感と知識の有無が、部下や顧客からの信頼に直結するのです。
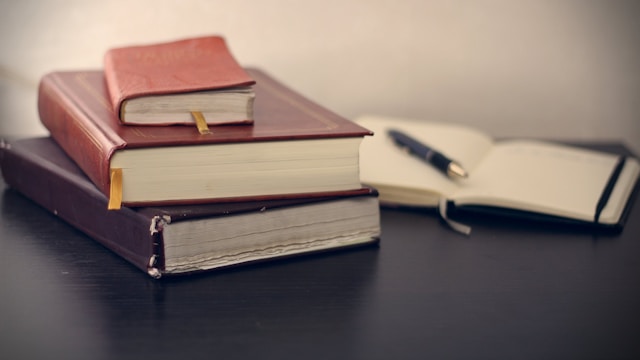
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=21512008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5215%2F9784502535215_1_6.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=21528227&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5314%2F9784502535314_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント