1. 品質管理の勝敗は“見える化”で決まる
あなたが管理職を目指しているなら、現場の数字をただ報告するだけでは足りません。
数字を“分析”し、“予測”し、“改善”につなげる力こそが評価されるのです!
そんな武器の一つが U管理図。
欠陥率の変化を的確に捉え、改善のタイミングを逃さないためのツールです。
そして、このスキルは製造業だけでなく、サービス業やIT、営業部門でも応用可能!
不良品の発生傾向を抑えられれば、コスト削減と顧客満足度向上という二兎を同時に狙えます。
2. U管理図とは?
U管理図は、単位あたりの欠陥数(欠陥率)を時系列で管理するための統計的手法です。
ポイントは、サンプルサイズが一定でなくても使えるということ。
これにより、現場の実態に沿った欠陥管理が可能になります。
- 横軸:時間(またはロット番号)
- 縦軸:単位あたりの欠陥率(u値)
- 中央線(CL):全体の平均欠陥率
- 管理限界(UCL / LCL):工程の“正常範囲”を示す
3. U管理図の作り方(5ステップ)
ステップ1:データ収集
期間ごとに、
- 検査数(n)
- 欠陥数(d)を記録します。
ステップ2:各期間の欠陥率(u)を計算
\(u_i = \frac{d_i}{n_i}\)例:欠陥数8、検査数120なら、
\(u = \frac{8}{120} \approx 0.0667(約6.67%)\)ステップ3:平均欠陥率(ū)を計算
- 総欠陥数(D) すべての期間の欠陥数を合計します。 例:5 + 8 + 3 + 6 + 4 = 26
- 総検査数(N) すべての期間の検査数を合計します。 例:100 + 120 + 80 + 110 + 90 = 500
- 平均欠陥率(ū)\(\bar{u} = \frac{D}{N} = \frac{26}{500} = 0.052\)つまり、全体での平均欠陥率は5.2%です。
ステップ4:管理限界を計算
U管理図では、サンプルごとにnが異なるため、UCL / LCLも変動します。
\(UCL_i = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}\) \(LCL_i = \bar{u} – 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}\)※LCLが負の場合は0にします。
ステップ5:グラフ作成と分析
- CL(中央線):\(\bar{u}\)
- 各期間のUCL / LCLを計算してプロット
- u値がUCLを超えたら工程異常の可能性大!
4. 実務での活用事例
事例:製造部門での活用
ある工場で、毎日100〜150個の製品を検査し、欠陥数を記録しました。
U管理図を作成すると、第8日目と第15日目にUCLを大きく上回る欠陥率が発生!
調査すると、特定の部品ロットに不良が集中していたことが判明。
仕入れ先の変更と検品強化で、その後の欠陥率は平均値以下に安定しました。
事例:コールセンターでの活用
「欠陥」をクレーム件数に置き換えて管理。
1日あたりの応対件数を母数にして、クレーム発生率をU管理図で監視。
特定の曜日にクレーム率が急上昇する傾向を発見し、要員配置とマニュアルを見直すことで、クレーム件数が2ヶ月で30%減少しました!
5. 管理職候補へのメッセージ
U管理図は単なる統計ツールではありません。
それは、現場改善のナビゲーションシステムです。
数字を“読む”力を身につければ、あなたは現場の信頼を勝ち取り、
上層部からも「任せられる人材」と見なされます!
さらに、このスキルを活かして
- 社内研修の講師
- 改善プロジェクトのリーダーとして活躍すれば、昇進や社内評価にも直結します。
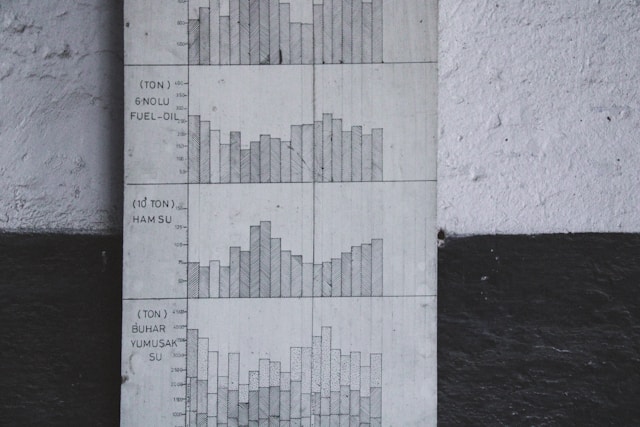


コメント