■ はじめに — あなたの現場、「数字で語れていますか?」
「不良が多い気がするけど…、何をどう改善すべきか分からない」
そんな経験、ありませんか?
現場を任される管理職になるためには、感覚ではなく数字で語れる力 が必須です。
しかも、その数字を誰が見ても一目で分かる形にすることが、信頼されるリーダーの第一歩!
そこで登場するのが np管理図。
これは、一定数のサンプルを取って、その中の不良“個数”を直接監視するシンプルかつ強力なツールです。
使いこなせば、「現場の安定度」が一目で分かり、改善のタイミングを逃しません!
■ np管理図とは? — シンプルだからこそ強い!
np管理図は、毎回同じサンプルサイズで検査を行う場合に使う管理図です。
つまり、サンプル数が「毎回同じとき」に使う不良品の「個数」を監視する管理図です。
サンプルごとの「不良数」をそのままプロットし、工程が安定しているか(管理状態か)を判断します!
特徴はとてもシンプルで、
- 不良の割合ではなく個数を直接監視
- サンプル数が一定だから計算が簡単
- 現場のスタッフにも説明しやすい
つまり、現場全員が理解できる改善ツールなんです!
いつ使うか(適用条件)
- 各サンプルの大きさ n が一定であること(例:毎日100個ずつ抜き取り検査する)。
- 監視対象は 不良品の“個数”(数えられる属性データ)。
- 二項分布の近似として正規分布を使うので、np̄ ≥ 5 と n(1−p̄) ≥ 5(目安)が満たされていることが望ましい。
※もし n が変動するなら p管理図 を使うのが原則です(後で補足します)。
数式(基本形) — まずは公式を示します
- 全期間の総不良数:\(D = \sum d_i\)
- 全期間の総検査数:\(N = \sum n_i\)(ただし np 管理図は n_i がすべて同じ=n)
- 全体の平均不良率:\(\displaystyle \bar{p} = \frac{D}{N}\)
- 平均不良数(中央線:CL):\(\displaystyle \overline{np} = n \cdot \bar{p}\)
- 管理限界(上下):\(\begin{aligned} UCL &= \overline{np} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})},\\[4pt] LCL &= \overline{np} – 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}, \end{aligned}\)ただし LCL < 0 なら LCL = 0。
■ 作り方 — 3ステップで完成!
では早速、作り方を実践形式で見ていきましょう。
例として「毎日100個の製品を抜き取り検査」するケースを考えます。
ステップ1:平均不良率を求める
- 各日ごとの不良個数を合計(例:10日間で合計50個)
- 全検査数を合計(例:100個 × 10日 = 1,000個)
- 平均不良率 \(\bar{p} を計算\bar{p} = \frac{\text{総不良数}}{\text{総検査数}} = \frac{50}{1000} = 0.05\)(5%)
ステップ2:中央線(CL)を求める
中央線 = 平均不良数 = \(n \times \bar{p}\)
例では
\(CL = 100 \times 0.05 = 5\)つまり、平均すると1日あたり不良は5個。
ステップ3:管理限界(UCL, LCL)を計算
公式はこうです!
\(UCL = CL + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}\) \(LCL = CL – 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}\)ただし、LCL が負なら0にします。
例の計算:
- \(n\bar{p}(1-\bar{p}) = 100 \times 0.05 \times 0.95 = 4.75\)
- \(標準偏差 = \sqrt{4.75} \approx 2.18\)
- \(3σ = 3 \times 2.18 \approx 6.54\)
- \(UCL = 5 + 6.54 \approx 11.54\)
- \(LCL = 5 – 6.54 \approx -1.54 → 0\)
結果:
UCL = 約11.54、CL = 5、LCL = 0
丁寧な手順と具体例
条件(例)
- 毎日抜き取り個数 n = 100(一定)
- 10日分の不良数データ:5, 8, 3, 6, 4, 7, 2, 5, 6, 4
ステップA:総不良数と総検査数を計算
- 総不良数 D を足す:
- 5 + 8 = 13
- 13 + 3 = 16
- 16 + 6 = 22
- 22 + 4 = 26
- 26 + 7 = 33
- 33 + 2 = 35
- 35 + 5 = 40
- 40 + 6 = 46
- 46 + 4 = 50→ D = 50
- 総検査数 \(N = n \times \text{日数} = 100 \times 10 = 1000\)
ステップB:平均不良率\( \bar{p}\)
\(\bar{p} = \frac{D}{N} = \frac{50}{1000} = 0.05\)(=全体の不良率は 5.0%)
ステップC:中央線(平均不良数) \(\overline{np}\)
\(\overline{np} = n \cdot \bar{p} = 100 \times 0.05 = 5\)(=1サンプルあたり平均不良数は 5個)
ステップD:標準偏差の中身を計算(分散の項)
\(n\bar{p}(1-\bar{p}) = 100 \times 0.05 \times (1 – 0.05) = 100 \times 0.05 \times 0.95\)計算:
- \(0.05 \times 0.95 = 0.0475\)
- \(100 \times 0.0475 = 4.75\)
標準偏差は\( \sqrt{4.75}。\)
\(\sqrt{4.75} \approx 2.179449\)(小数は概算)
3σ(3倍):
\(3\sigma = 3 \times 2.179449 \approx 6.538347\)ステップE:上下管理限界を計算
\(UCL = 5 + 6.538347 \approx 11.538347\) \(LCL = 5 – 6.538347 \approx -1.538347 \rightarrow \text{LCLは0に修正}\)→ 管理限界は UCL ≈ 11.54、LCL = 0、CL = 5。
ステップF:結果の判定
上の10日間の不良数は [5,8,3,6,4,7,2,5,6,4]。どれも 11.54 を超えていないので、この期間は統計的には「工程は管理状態にある」と判断できます(ただしトレンドや連続性の規則も要チェック)。
なぜ np 管理図の公式がこうなるのか
- 不良品の個数は 二項分布 \(\text{Bin}(n, p) \)に従う(n 個の試行で成功確率 p のときの成功回数)。
- 二項分布の平均は n p、分散は n p (1-p)。
- 中央線は平均 n\bar{p}。標準誤差は\( \sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}\)。
- 管理図では ±3σ を用いるので、上下は上の式になります。
- 正規近似を用いる点に注意(\(np̄ と n(1-p̄)\) が十分大きいと正規近似が妥当です)。
np 管理図と p 管理図の違い(要点)
- np 管理図:サンプル数 n が 一定 のときに不良数(個数)を直接プロット。
- p 管理図:サンプル数 n が 変動するときに不良率\( p_i = d_i / n_i \)をプロット。
- p 管理図の管理限界:\(\bar{p} \pm 3\sqrt{\dfrac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}(n_i が各サンプルで異なる)\)
- np 管理図は p 管理図の値を n 倍したものと等価(nが一定のため)。
実務での注意点と運用のコツ(管理職向け)
- n が一定か必ず確認!もし一定でなければ np 管理図は間違いの元。p 管理図に切り替えましょう。
- サンプル数が小さいと検出力が落ちる(有意な変化が見えにくい)。
- \(p̄\)(不良率)が非常に小さい(希少事象)なら、Poisson近似やg管理図の検討が必要。
- LCL が負になる場合は 0 に修正。しかし、LCL=0 ばかりならグラフの判定力が落ちます。
- トレンドやシフトに注意:単一点だけでなく、連続した上昇、規則的パターンも危険信号です(Western Electric ルールなどを併用)。
- 原因調査は即時に:UCL超えや異常パターンは「原因の探索」をすぐに開始。5 Why、パレート、工程チェックシートを使いましょう。
■ 使い方のコツ — 管理職への“見える化”スキル
- 異常値は即行動! UCLを超えたら「何が起きたか」をすぐに調査。放置は悪化のもと!
- 連続した傾向も要注意! 数値が徐々に上昇している…これも改善サインです。
- 会議で使える武器に! 管理図を会議資料に入れれば、感覚論からデータ論へシフトできます。
Excelでの実装手順(すぐ使える)
- 列A:日付/ロット番号
- 列B:検査数 n(npでは一定)
- 列C:不良数 d
- 列D:不良率 =C2/B2(オプション)
- 列E:計算した \(\bar{p}\)(定数)= =SUM(C:C)/SUM(B:B)
- 列F:CL =B2*$E$1`(n\(p̄\))
- 列G:UCL =F2 + 3*SQRT(B2*$E$1*(1-$E$1))
- 列H:LCL =MAX(0, F2 – 3*SQRT(B2*$E$1*(1-$E$1)))
- グラフ:列F,G,Hと列Cを折れ線/散布図でプロット。
異常が出たときの実務的アクション例
- 即時停止(安全や重大品質影響がある場合)
- 原因仮説の立案(材質、設備、工程、人為ミス、外部要因)
- データ掘り下げ(該当ロットの詳細、前後の工程条件、作業者情報)
- 暫定対策→恒久対策→効果測定(改善前後を再度管理図で確認!)
■ 参考事例 — “昇進”につながった活用例!
ある製造ラインの主任Aさんは、np管理図を使って半年間の不良動向を記録。
異常発生時はすぐに原因分析し、「部品ロット不良」が原因であることを突き止めました。
結果、年間不良率を3.2%から1.0%に改善!
この成果が評価され、なんと翌年に係長へ昇進したのです!
ポイントは「現場の安定度を見える化し、改善を数字で示す」こと。
これが、上司や経営層に響くんです!
■ おすすめ書籍
- キーワード:「np管理図」「品質管理 不良数」「製造業 改善事例」
■ まとめ — データで語る人材は昇進が早い!
- np管理図は、サンプルサイズが一定のときに「不良個数」を直接監視する最も直感的な管理図!
- 公式は \(CL = n p̄, UCL/LCL = n p̄ ± 3√(n p̄ (1−p̄))\)。
- ただし nが一定であること と\( np̄ \)と\( n(1−p̄) \)が十分大きいこと を必ず確認して使ってください。
np管理図は、シンプルでありながら「現場を数字で見える化」できる強力な武器です。
使いこなせば、不良低減だけでなく、あなたの評価とキャリアアップに直結します!
さあ、次の一手はあなたの番です。
今日から、np管理図で現場を掌握し、昇進ロードを走り抜けましょう!
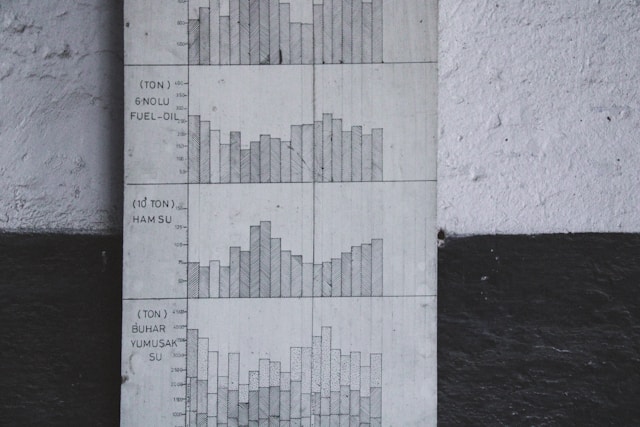


コメント