みなさん、業績や目標の達成状況を分析していると、「なぜこの数値がこうなったのか?」と疑問に思うことはありませんか? 例えば、売上が落ちた、利益が伸び悩んでいる、あるいは顧客満足度が低下している……。こうした重要指標の変動には、必ず原因(ファクター)があります!
しかし、ここで注意が必要です。闇雲に手を打つのではなく、「本当に影響度の大きい要因は何か?」を見極めることが大切です。そこで活用したいのが 「ファクター分析」 です!
① 重要指標の分析を深める!
問題が発生したとき、その原因を特定するために、まずは トレンド分析 を行います。そこで異変を察知したら、次のステップとして 「どの要因がどれくらい影響しているのか?」 を深掘りしましょう。
なぜなら、影響度の小さい要因ばかりにエネルギーを割いても、 「労多くして益少なし!」 だからです。例えば、売上が低下しているとき、「新規顧客の減少」と「リピート率の低下」のどちらがより大きな影響を及ぼしているのかを明確にしなければ、的確な対応策を打てません!
さらに、 「定量的に把握する」 ことが極めて重要です。なぜなら、 先入観にとらわれてしまうと、誤った意思決定をしてしまう 可能性があるからです! 仮に先入観が正しかったとしても、数値データで裏付けることで、チームや上司への説明がスムーズになります。人それぞれ重要視するポイントが違うからこそ、 データをもとに共通認識を持つ ことが不可欠なのです!
② 実際にファクター分析をするときの留意点
〜「なぜ?」を深掘りし、要因を漏れなく洗い出す!〜
では、実際にファクター分析を行う際、どのような点に気をつけるべきでしょうか?
最も重要なのは、「変動要因を漏れなく洗い出すこと!」 です!
なぜ、要因の漏れが危険なのか?
もし、考えうるすべての要因を調査したにもかかわらず、
 「どうしても重要指標の変化が説明できない……」
「どうしても重要指標の変化が説明できない……」
という状況になったら、それは 「要因の洗い出しに漏れがある」 という証拠です!
たとえば、こんな経験はありませんか?
 事例:「利益が減少した原因を探る」
事例:「利益が減少した原因を探る」
あなたは、利益が減少した原因を探ろうとしています。
まず、よくある原因として 「売上の減少」 や 「原価の増加」 をチェックしました。
しかし、それだけでは説明がつかない……。
「おかしいな…ほかに何があるんだろう?」
よくよく調べてみると、「販促費が増えていた」 や 「顧客単価が下がっていた」 ことに気づきました!
もしこの2つを見落としていたら?
➡ 「売上はそれほど落ちていないのに利益が減った理由」が分からず、誤った対策を打ってしまう可能性大!
実践的なアクション:要因をモレなく洗い出す方法!
では、要因の漏れを防ぐにはどうすればいいのでしょうか?
以下の 3つのステップ で、抜け漏れを徹底的に防ぎましょう!
 ステップ1:「なぜ?」を3回以上繰り返して深掘りする!
ステップ1:「なぜ?」を3回以上繰り返して深掘りする!
(これがファクター分析の基本!)
「売上が落ちた」「利益が減った」という事象だけを見ても、表面的な原因しか分かりません!
 具体例:「利益が減少した原因を深掘り」
具体例:「利益が減少した原因を深掘り」
 「なぜ利益が減った?」 → 「売上が減少したから」
「なぜ利益が減った?」 → 「売上が減少したから」
 「なぜ売上が減った?」 → 「顧客単価が下がったから」
「なぜ売上が減った?」 → 「顧客単価が下がったから」
 「なぜ顧客単価が下がった?」 → 「競合が価格を下げたから」
「なぜ顧客単価が下がった?」 → 「競合が価格を下げたから」
➡ ここでやっと、「競合の影響が原因だった!」 という本当の問題が見えてきます!
 おすすめアイテム
おすすめアイテム
 ホワイトボードと付箋 → 「なぜ?」を付箋に書いて貼ると、チームで議論しやすい!
ホワイトボードと付箋 → 「なぜ?」を付箋に書いて貼ると、チームで議論しやすい!
 マインドマップツール(XMind, MindMeister) → 要因を階層化し、整理しながら深掘りできる!
マインドマップツール(XMind, MindMeister) → 要因を階層化し、整理しながら深掘りできる!
 ステップ2:「MECE」で要因を整理し、抜け漏れを防ぐ!
ステップ2:「MECE」で要因を整理し、抜け漏れを防ぐ!
MECE(ミッシー)とは、「モレなくダブりなく(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)」 という考え方。
 利益の変動要因をMECEで整理すると…
利益の変動要因をMECEで整理すると…
 売上の変動(売上単価 × 販売数)
売上の変動(売上単価 × 販売数)
 コストの変動(固定費・変動費)
コストの変動(固定費・変動費)
 外部要因(市場の動向、競合の影響)
外部要因(市場の動向、競合の影響)
➡ このように分類することで、漏れを防ぐことができます!
 おすすめツール
おすすめツール
 ExcelやGoogleスプレッドシート → MECEで表を作り、漏れなくチェック!
ExcelやGoogleスプレッドシート → MECEで表を作り、漏れなくチェック!
 ホワイトボード+カテゴリ別のマグネットシート → 目に見える形で整理すると理解しやすい!
ホワイトボード+カテゴリ別のマグネットシート → 目に見える形で整理すると理解しやすい!
 ステップ3:「ゼロベース思考」で新しい視点を取り入れる!
ステップ3:「ゼロベース思考」で新しい視点を取り入れる!
「もう全部の要因を洗い出した!」と思っても、実は固定観念にとらわれているだけかも?
 ゼロベース思考の具体例
ゼロベース思考の具体例
 悪い例:「利益が減った原因は、どうせ売上の低下でしょ?」
悪い例:「利益が減った原因は、どうせ売上の低下でしょ?」
 良い例:「売上以外の要因(例えば人件費や税金)は影響していないか?」
良い例:「売上以外の要因(例えば人件費や税金)は影響していないか?」
➡ 「常識にとらわれず、ゼロから考え直す!」 これがポイントです!
 役立つアイテム
役立つアイテム
 ブレインストーミングノート → 新しい視点をどんどん書き出す!
ブレインストーミングノート → 新しい視点をどんどん書き出す!
 チームディスカッション → 他のメンバーの意見を聞くことで、新しい気づきを得られる!
チームディスカッション → 他のメンバーの意見を聞くことで、新しい気づきを得られる!
ファクター分析を成功させる3つのコツ!
ファクター分析の最大の落とし穴は、「要因の洗い出しに漏れがあること」です。
これを防ぐためには、次の 3つのステップ を実践しましょう!
 ステップ1:「なぜ?」を3回以上繰り返して深掘り!
ステップ1:「なぜ?」を3回以上繰り返して深掘り!
 ステップ2:「MECE」で要因を整理し、抜け漏れを防ぐ!
ステップ2:「MECE」で要因を整理し、抜け漏れを防ぐ!
 ステップ3:「ゼロベース思考」で新しい視点を取り入れる!
ステップ3:「ゼロベース思考」で新しい視点を取り入れる!
この3つを押さえれば、本当の原因を特定し、効果的な対策を打つことができます!
③ ファクター分析をチャート化するときのポイント
〜視覚的にわかりやすく整理し、分析結果を最大限に活かす〜
ファクター分析の結果を効果的に活用するためには、 「パッと見て直感的に理解できるチャート」 を作ることが重要です! 特に 「+(プラス)」の要因と「−(マイナス)」の要因を区別すること」 がカギになります。
なぜなら、 プラス要因とマイナス要因が混ざっていると、「どこが問題なのか?」「何を改善すべきなのか?」が分かりにくくなる からです。
具体的なチャート作成のポイント
 1. 色分けをして、一目でプラス・マイナスを区別!
1. 色分けをして、一目でプラス・マイナスを区別!
「色の使い方次第で、伝わりやすさが劇的に変わる!」
たとえば、利益の増減要因を分析するとき、次のように色分けすると分かりやすくなります。
| 要因 | 影響 | 色の例 |
|---|---|---|
| 売上アップ | +500万円 | 青(プラス) |
| コスト削減 | +200万円 | 青(プラス) |
| 広告費増加 | −300万円 | 赤(マイナス) |
| 人件費増加 | −400万円 | 赤(マイナス) |
➡ 青(プラス)と赤(マイナス)をはっきり区別すると、どの要因が利益にプラスで、どの要因がマイナスかが一瞬で分かります!
 2. プラス要因とマイナス要因を「別々に表示」する!
2. プラス要因とマイナス要因を「別々に表示」する!
「棒グラフを作ったけど、プラスとマイナスがごちゃ混ぜで見にくい…」という経験はありませんか?
これを防ぐために、 プラス要因とマイナス要因を並べて比較するのではなく、別々のグラフや配置にする のがポイントです!
 良い例(わかりやすいチャート)
良い例(わかりやすいチャート)
 プラス要因(売上増・コスト削減)を左側に、マイナス要因(経費増・コスト増)を右側に配置!
プラス要因(売上増・コスト削減)を左側に、マイナス要因(経費増・コスト増)を右側に配置!
 積み上げ棒グラフで、どの要因がどれくらい寄与しているかを一目で分かるように!
積み上げ棒グラフで、どの要因がどれくらい寄与しているかを一目で分かるように!
 悪い例(見にくいチャート)
悪い例(見にくいチャート)
 プラスとマイナスが交互に並んでいて、全体の傾向がつかみにくい!
プラスとマイナスが交互に並んでいて、全体の傾向がつかみにくい!
 色が統一されていないので、どれがプラスでどれがマイナスか分かりにくい!
色が統一されていないので、どれがプラスでどれがマイナスか分かりにくい!
 3. 比較対象が複数ある場合の整理方法
3. 比較対象が複数ある場合の整理方法
分析対象が1つならシンプルですが、 複数の事業・製品・地域ごとに比較する場合は、チャートの整理が必要!
 例:事業別の利益変動要因分析
例:事業別の利益変動要因分析
 「A事業」「B事業」「C事業」それぞれのプラス要因・マイナス要因を並べて比較!
「A事業」「B事業」「C事業」それぞれのプラス要因・マイナス要因を並べて比較!
 事業ごとに異なる背景がある場合は、補足コメントを入れる!
事業ごとに異なる背景がある場合は、補足コメントを入れる!
➡ 「どの事業が最も影響しているのか?」がひと目で分かるようにすることが重要!
 おすすめツール
おすすめツール
・ PowerPointのスマートアート機能(比較チャート作成)
・ Googleスプレッドシートの「グループ化」機能(複数の要因を整理)
・ マグネットシート(ホワイトボードに貼りながら整理するのに便利!)
 4. 実際に作って「伝わるか?」チェックする!
4. 実際に作って「伝わるか?」チェックする!
最後に 「このチャート、本当に分かりやすい?」 をチェックしましょう!
 チェックリスト
チェックリスト
 初めて見る人でも、一瞬で「プラス」と「マイナス」の違いが分かるか?
初めて見る人でも、一瞬で「プラス」と「マイナス」の違いが分かるか?
 色分けやグルーピングが適切で、混乱しないか?
色分けやグルーピングが適切で、混乱しないか?
 必要なら、補足説明を入れているか?
必要なら、補足説明を入れているか?
チームメンバーや上司に見せて、 「これ、パッと見て分かりますか?」 と聞いてみるのも有効です!
分かりやすいチャートで意思決定を加速!
ファクター分析の結果を最大限活用するために、 「誰が見ても直感的に理解できるチャート」を作ることがポイント!
 チャート作成の4つのコツ
チャート作成の4つのコツ
 色分けをしてプラス・マイナスを明確に!
色分けをしてプラス・マイナスを明確に!
 プラス要因とマイナス要因を別々に表示!
プラス要因とマイナス要因を別々に表示!
 比較対象が複数ある場合は、分かりやすい整理を!
比較対象が複数ある場合は、分かりやすい整理を!
 実際に作って、伝わるかチェック!
実際に作って、伝わるかチェック!
適切なチャートを作れば、 分析結果の説得力が増し、適切なアクションにつながる こと間違いなし!
まとめ:ファクター分析を武器にしよう!
管理職を目指すあなたにとって、 問題の本質を正しく見極め、的確な施策を打つことは必須スキル! そのために、 ファクター分析を活用し、「本当に影響を及ぼしている要因は何か?」を見極めましょう!
最後に、ポイントをおさらい!
 重要指標の変動要因を深く分析する!
重要指標の変動要因を深く分析する!
 先入観にとらわれず、データで定量的に把握する!
先入観にとらわれず、データで定量的に把握する!
 変動要因を漏れなく洗い出す!
変動要因を漏れなく洗い出す!
 チャート化する際は、プラス・マイナスを区別して視覚的にわかりやすく!
チャート化する際は、プラス・マイナスを区別して視覚的にわかりやすく!
これらを意識するだけで、 意思決定の精度が格段に向上 します! さあ、ファクター分析を武器にして、次のステップへ進みましょう!
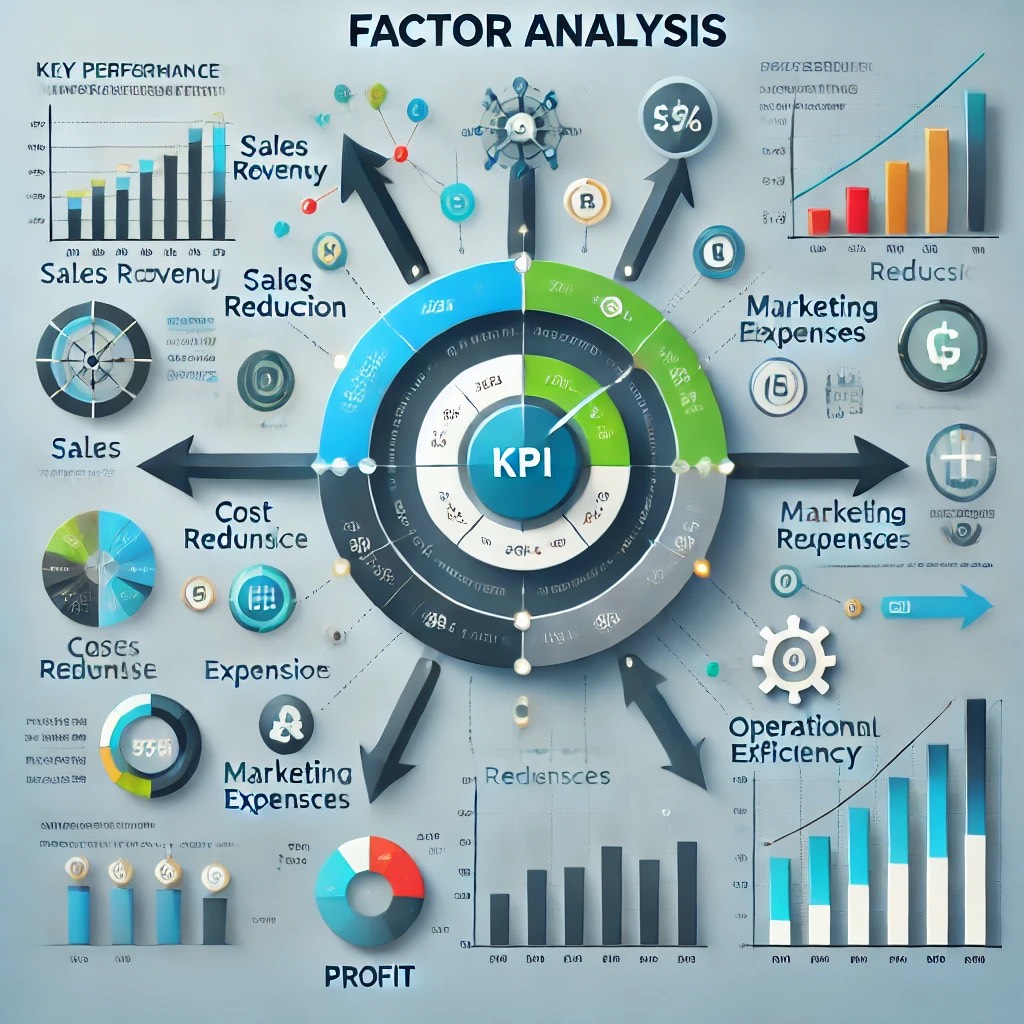
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=16880075&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3126%2F9784046003126_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント