こんにちは!管理職を目指すあなたにとって「問題解決力」は避けて通れないスキルですよね。それも、ただ目の前の問題を解決するだけじゃ足りません。これから求められるのは、一歩先を見据えた課題設定型の思考法です!
この記事では、「課題設定型の問題」とは何か、そしてどうやってその力を身に付けるのかを具体的に解説していきます。ぜひ最後までお付き合いくださいね!
発生型の問題を超えていこう!
まず、「課題設定型の問題」を理解するには、「発生型の問題」との違いを知ることが大切です。
発生型の問題とは、現在すでに発生しているトラブルやミスを指します。たとえば、納期に遅れているプロジェクトや、クレーム対応に追われる日々。こうした状況を放置すれば、当然、会社全体のパフォーマンスが低下してしまいます。
では、発生型の問題を解決するだけで十分なのでしょうか?答えはNOです!これだけ変化の激しい時代、現状を維持するだけでは競争に勝てません。だからこそ、次のステージである「課題設定型の問題」に進む必要があるのです。
課題設定型の問題とは?
「課題設定型の問題」とは、現状の基準を超えて、より高いレベルを目指すための問題設定を指します。つまり、現状に満足するのではなく、「もっと良くするにはどうすればいいのか?」を考え、具体的な目標を設定することです。
例:部門方針の見直し
たとえば、部門方針で「不良率2%を維持する」という目標が掲げられているとします。一見すると、達成可能な現実的な目標に見えますよね。でも、年度の後半になって環境が大きく変わったらどうでしょう?
競合他社がさらにコストを下げ、顧客の要求が厳しくなった場合、不良率2%では戦えないかもしれません。このとき、現状のルールを疑い、「不良率1%以下」を目指す新たな課題を設定するのが課題設定型の思考です。
なぜ現状を疑うことが重要なのか?
現在のルールや規定、標準は、過去のある時点で設定されたものに過ぎません。当時は有効だったとしても、時代や状況が変われば必ずしも適応し続けるとは限りません。
「このルール、本当に今の状況に合っているのか?」と問い続けることで、発生型の問題を超えて、さらに高い目標を設定することが可能になります。これが、管理職に求められる視座の高さと言えるでしょう!
課題設定型の問題解決力を鍛える方法
では、どうすれば課題設定型の思考力を鍛えることができるのでしょうか?ここでは、具体的なステップをいくつか紹介します。
1. 現状を正しく把握する
まずは、現状をデータや事実に基づいて冷静に分析しましょう。「問題がない」と思っている部分にも、改善の余地が隠れていることが多いものです。
2. 前提を疑う癖をつける
「これが当然」と思っていることほど疑ってみましょう。ルールや基準、プロセスが本当に最適かどうかを問い直す習慣をつけることが重要です。
3. 高い目標を設定する
目標設定の際には、少し背伸びをするくらいがちょうど良いです。「これを達成できたらすごい!」と思えるくらいの目標を掲げ、それに向けた行動計画を立てましょう。
4. チームを巻き込む
課題設定型の問題は、個人だけでは解決できません。チーム全体で共有し、同じ方向を目指すことで大きな成果を生み出します。
課題設定型の思考でキャリアアップを狙え!
課題設定型の問題解決力を身に付けることで、あなたの職場での価値は飛躍的に高まります。管理職として必要なスキルを磨き、会社の未来を切り開く存在となることができるのです。
さらに、このスキルは転職や昇進だけでなく、副業や起業など多岐にわたる場面で役立ちます。自分自身の可能性を広げるためにも、今日から「課題設定型の問題」にチャレンジしてみてください!
まとめ:課題設定型の問題を発見し、未来を変える!
いかがでしたか?この記事では、「課題設定型の問題」について詳しく解説しました。発生型の問題を解決するだけでなく、未来を見据えて課題を設定する力こそが、これからの時代に求められるスキルです。
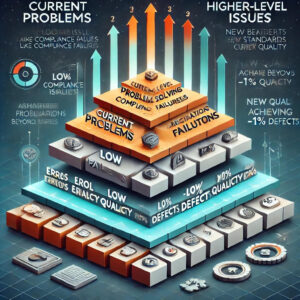



コメント