「業務改革を進めているけど、どうも場当たり的になってしまう…」
そんな悩みを抱えていませんか?
目についた問題を次々と改善するのは決して悪いことではありません。しかし、根本的な業務の構造を理解せずに進めると、一時的な改善にとどまり、長期的な業務負担の削減につながらないことも…。
この記事では、業務の構造を踏まえた上で、体系的に業務改革を進める方法を徹底解説!
「業務1回あたりの時間 × 業務回数 = 業務量」
このシンプルな公式を軸に、どのように業務量を削減すればいいのかを具体的に考えていきます。
最後まで読めば、あなたの職場で「本当に効果のある業務改革」を実践できるようになりますよ!
業務改革の基本方針:業務量を削減せよ!
業務改革の目的の一つは、「省力化」です。つまり、業務量を減らし、より少ないリソースで高い成果を出せるようにすること。
ここで、業務量は以下の2つの要素で決まります。
1. 業務1回あたりの時間
2. 業務回数
この2つを減らすことができれば、業務量の削減につながります!
でも、「ただ単に時間を短縮すればいい」「業務回数を減らせばいい」と考えていてはダメなんです…。
なぜなら、同じ業務でも処理時間は状況によってバラバラ!
「早く終わる場合」「普通の場合」「めちゃくちゃ時間がかかる場合(悲観ケース)」の3つが存在し、これを無視して改革を進めると、思うような効果が出ません。
では、具体的にどうすればいいのか?
次のセクションで深掘りしていきます!
業務1回あたりの時間を短縮するカギは「悲観ケース」の削減!
業務時間を短縮する際に注目すべきなのは、「悲観ケース」です。
悲観ケースとは、業務が通常の何倍も時間がかかる例外的なケースのこと。
たとえば、申込書の処理業務を考えてみましょう。
• 通常の申込書処理(最頻ケース):5分で完了!
• ミスがある申込書の処理(悲観ケース):30分かかる…!
このように、業務1回あたりの時間が大幅に変わるのが悲観ケースの特徴です。
驚くことに、業務回数全体の1割にも満たない悲観ケースが、業務量全体の50%を占めることも珍しくありません!
つまり、この悲観ケースを減らすことができれば、業務量を大幅に削減できるんです。
悲観ケースはなぜ発生するのでしょうか?
悲観ケースが発生する主な理由は、業務の上流工程で発生する不備やエラーが、その後の処理に大きな影響を与えるためです。具体的には以下のような要因が挙げられます。
• 入力ミスや不備
例えば、営業担当者が申込書のチェックを十分に行わず、誤った情報や必要な記載が抜けた状態で書類が提出されると、その後の訂正作業に大幅な時間がかかります。
• 書類の設計不良
申込書自体の設計が分かりにくく、記入ミスを誘発する場合もあります。書類のフォーマットや記載内容が複雑だと、正確な記入が難しくなり、後でエラーが発覚した時に修正に多くの時間を要することになります。
• 必要書類の不備・不足
必要な書類が揃っていない、または不足している場合、何度も差し戻しが発生し、業務プロセス全体が遅延します。これも一例の悲観ケースとして、業務時間を大幅に増加させる原因となります。
• 情報伝達の不足
業務の関係部門間での情報共有が不十分であると、初期段階での不備が見逃され、その結果、後続の工程での手戻りが増えます。これにより、通常よりも時間がかかる処理が増えてしまいます。
• プロセスの複雑さ
業務フロー自体が複雑で、各工程に多くのチェックや確認が必要な場合、1回あたりの業務にかかる時間が大幅に増加する可能性があります。
これらの要因は、個別に発生する場合もあれば、複数が重なって発生することもあり、その結果、全体の業務回数のごく一部(1割未満)であっても、業務全体の50%もの時間を消費してしまうことがあります。
つまり、悲観ケースが発生する根本原因は、業務の初期段階でのミスや不備、さらには業務プロセス自体の非効率な設計にあると言えます。これらの問題に対処するためには、業務全体のプロセスを網羅的に見直し、関係部門と連携して上流工程の改善に取り組むことが不可欠です。
悲観ケースの発生原因と対策!
悲観ケースの多くは、業務の上流工程で発生した問題が下流に影響を与えていることが原因です。
例えば、申込書の処理が遅れる原因を深掘りすると…
• 営業担当者のチェックミスで、内容不備の書類が提出される
• 申込書の設計そのものがわかりにくく、記入ミスが多発する
• 必要書類が揃っていないため、何度も差し戻しが発生
こんな問題が考えられます。
解決策として、以下のような施策が有効です!
 営業担当者向けに「申込書チェックリスト」を作成し、ミスを未然に防ぐ!
営業担当者向けに「申込書チェックリスト」を作成し、ミスを未然に防ぐ!
 申込書のデザインを見直し、間違えにくいフォーマットに変更する!
申込書のデザインを見直し、間違えにくいフォーマットに変更する!
 必要書類の確認フローを簡素化し、事前チェックを徹底する!
必要書類の確認フローを簡素化し、事前チェックを徹底する!
こうした改善を行うことで、悲観ケースの発生を抑え、業務時間を短縮できます。
業務回数を削減するには「ルール変更」がカギ!
次に、業務回数を削減する方法を考えましょう。
最も効果的なのは、「業務ルールの見直し」です!
なぜなら、多くの業務は「昔からの慣習」で行われており、今の実態に合っていない非効率なルールがそのまま残っていることがあるからです。
例えば…
• 確認作業が過剰で、何度も同じ内容をチェックしている
• 決裁フローが複雑で、いちいち管理職の承認が必要
• 不要になった業務がそのまま続いている
こうした無駄な業務は、業務ルールを変更するだけで一気に削減できます!
業務ルールを見直すポイント!
 「この確認、本当に必要?」を問い直し、確認回数を減らす!
「この確認、本当に必要?」を問い直し、確認回数を減らす!
 「決裁基準を見直し」、一定の権限を現場に委譲する!
「決裁基準を見直し」、一定の権限を現場に委譲する!
 「業務の目的」を見直し、不要な作業を廃止する!
「業務の目的」を見直し、不要な作業を廃止する!
たとえば、決裁基準を見直して現場に権限を与えれば、管理職の決裁業務が減り、意思決定がスピードアップ!
このように、業務ルールを適切に変更することで、業務回数を大幅に削減できるのです!
まとめ:業務改革は「悲観ケース」と「ルール」に着目せよ!
ここまでのポイントをまとめると…
 業務1回あたりの時間を短縮するには、悲観ケースを削減する!
業務1回あたりの時間を短縮するには、悲観ケースを削減する!
 業務回数を減らすには、業務ルールを見直す!
業務回数を減らすには、業務ルールを見直す!
この2つを実践すれば、業務改革の成果を最大化できます!
「目の前の課題に対処するだけ」ではなく、業務全体の構造を俯瞰して改革に取り組むことが重要です。
あなたの職場でも、まずは「悲観ケースの特定」と「業務ルールの見直し」から始めてみてください!
そうすれば、驚くほど効率的に業務が改善されるはずですよ!
業務改革は、一朝一夕で終わるものではありません。しかし、着実に進めれば、必ず成果が出ます!
さあ、今すぐ改革を始めましょう!
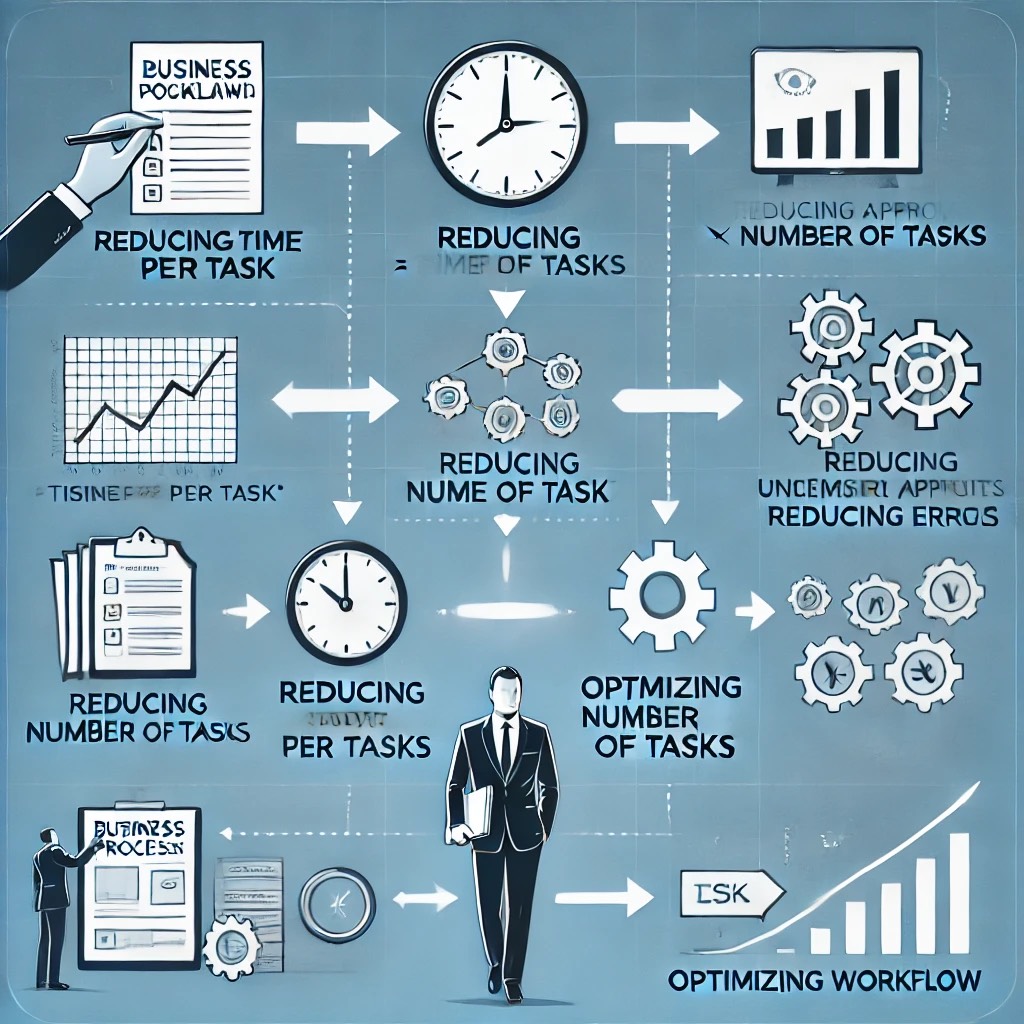
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4390cd2b.ad50cb16.4390cd2c.394d517b/?me_id=1213310&item_id=16850371&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1248%2F9784862761248_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント